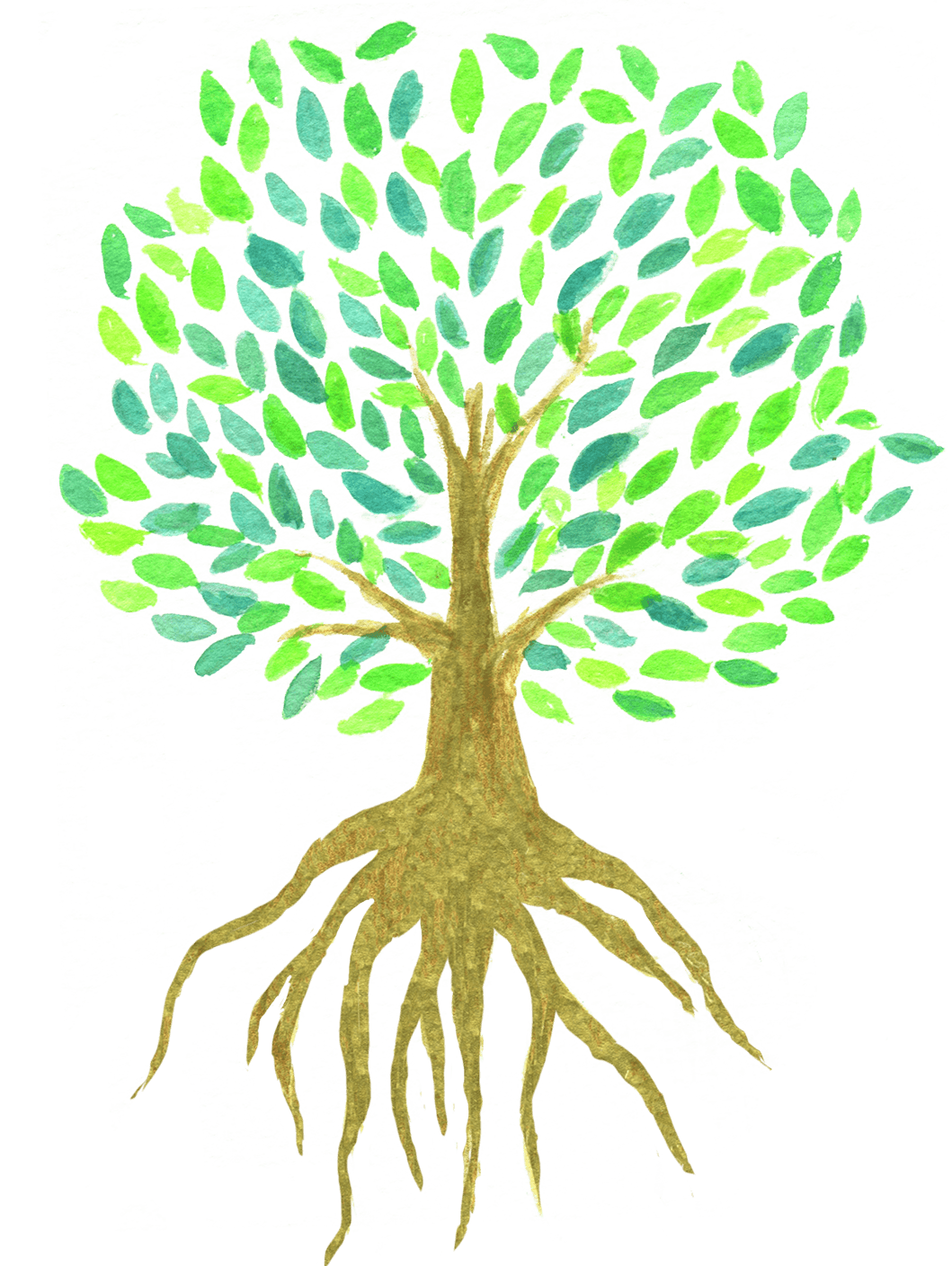なぜ昔の家は「夏涼しく冬寒い」?
2025.11.05
ブログ

🏠なぜ昔の家は「夏涼しく冬寒い」?
〜昔の知恵と現代の家づくり〜
「昔の家は夏は涼しいけれど、冬は寒い」とよく言われます。
実際、昔ながらの木造住宅に入ると、風が抜けて心地よい一方で、
冬はすきま風が冷たく感じられた方も多いのではないでしょうか。
この違いは、家のつくり方と暮らしの工夫にあります。
■ 昔の家は“夏中心”の家づくりだった
日本は高温多湿の気候。
昔の家づくりでは、何よりも「風通し」と「日差しの遮り方」が重視されていました。
・大きな軒(のき)で直射日光を避ける
・南北に風が抜けるように窓を配置する
・土間や縁側で温度を調整する
こうした工夫で、風が通り抜ける“涼しい家”を実現していたのです。
木や土壁、い草の畳など、自然素材の調湿効果も大きな役割を果たしていました。
■ その代わり、冬はとても寒かった
しかし、昔の家は断熱や気密という考えがほとんどありませんでした。
隙間が多い構造のため、冷たい外気が室内に入りやすく、
どんなに火鉢やこたつで温めても、家全体はなかなか暖まらなかったのです。
それでも当時は、家族がひとつの部屋に集まり、
火を囲みながら過ごす“暮らしの知恵”で寒さを乗り越えていました。
■ 現代の家づくりに生きる「昔の知恵」
今の家は高気密・高断熱が当たり前。
冷暖房効率が高く、1年を通して快適に過ごせるようになりました。
けれども、昔の家づくりに学ぶことも多くあります。
たとえば「風の通り道」や「軒の深さ」「窓の向き」。
これらを意識して設計することで、
エアコンに頼りすぎない、自然で心地よい住まいが生まれます。
🪟1. 風の「入口」と「出口」をセットで考える
風は、必ず入る窓と出る窓がないと流れません。
・風上(主に南側や東側)に大きめの窓を設ける
・風下(北側や西側)に小さめの窓や換気口を設ける
こうすることで空気が自然に流れ、熱や湿気をためにくくなります。
🏠2. 室内の“風の道”をつくる
家の中でも空気が滞ると湿気や熱がこもります。
・廊下や階段を通って風が抜けるような間取り
・ドア上部に開口を設ける
・引き戸やスリット入りの建具で気流を分断しない
こうした工夫で、閉めきったときでも空気がゆるやかに流れます。
🌤3. 縦方向の通風を利用する
風は横だけでなく上下方向にも流れる性質があります。
・吹き抜けや階段ホールを利用して熱い空気を上に逃がす
・天窓や高窓を開けて上昇気流を利用する
これにより、1階から2階へ自然な空気の流れが生まれます。
🌳4. 外構や植栽で風をコントロール
建物周辺の環境も通風に大きく影響します。
・庭やデッキの植栽でやわらかく風を導く
・隣家や塀との間を風が抜ける距離にする
・深い軒や庇で直射日光を避けながら通風を確保
外と内の一体設計で、季節ごとの風を上手に取り込めます。
■ 暮らしの心地よさは“数字”だけでは測れない
断熱性能や気密性能も大切ですが、
風・光・素材など、五感で感じる心地よさも家づくりには欠かせません。
昔の家が教えてくれるのは、
「自然と共に暮らす」という感覚そのもの。
明神綜合建設では、こうした“昔の知恵”を現代の技術と融合させ、
四季を感じながら快適に暮らせる家づくりを大切にしています。
🪟まとめ
-
昔の家は「風通し重視」=夏に強く冬に弱い構造
-
現代の家は「断熱・気密重視」=年間を通して快適
-
昔の知恵を取り入れた“風が通う設計”が理想的